味の素AGF株式会社資料作成も戦略立案もAIと共に。「Nomatica」で変わる働き方


味の素AGF株式会社
味の素AGF株式会社は、1973年に設立され、コーヒーを中心に飲料・食品の製造販売を行う企業です。
いつでもどこでも、最高のおいしさで一杯の価値を提供する「日本発の愛される嗜好飲料メーカー」を目指しています。
コーヒーを中心とした事業を通じて、「人と人とのつながり」、「地球環境との共生」をはじめとするサステナブルな社会の実現に貢献すると同時に、Relax(くつろぎ)、Reset(心の整え)、Refresh(気分一新)の提供を通じて、「ココロ」と「カラダ」の健康に貢献します。
概要
本インタビューでは、味の素AGF株式会社の皆様に、AIエージェントサービス「Nomatica」導入の背景から、実際の活用事例、そして今後の展望までを詳しく伺いました。
導入のきっかけは「自社データを活用した専用AIエージェント構築」と「マルチAIエージェントによる実務に直結する提案力」。
実務の現場では、
- Deep Researchでゼロの情報を“1”に変える調査力
- 報告書や資料の自動作成による業務効率化
- 専門型AIエージェントによる戦略立案の型打ち
といった形で、日々の業務を強力に支援。
社員の方々からは「バイアスのない調査ができた」「外部パートナーとの打ち合わせのための初期整理が不要になった」「専属コンサルタントがそばにいるようだ」といった声が寄せられています。
本日は日頃どのように「Nomatica」を活用されているか、その効果や今後の展望についてお話を伺いたいと思います。では、まずは自己紹介からお願いします。
平さん:導入を主導しているマーケティング高度化グループの担当でした。2025年7月から別部署に移っています。
山本さん:導入当時は平さんと一緒に実務を担当していて、今はマーケティング高度化グループでAI活用の担当を引き継いでいます。
岡原さん:私は導入当時から製品まわりのリサーチや生活者調査を担当しています。使い方をシェアする立場と、現場で活用する立場の両方ですね。
斎藤さん:ソリューションビジネス部で、コーヒー以外の飲料商品の企画・開発を担当しています。
導入当時の背景を教えてください。
平さん:マーケティングの高度化を模索する中で、直近ではAIの活用が課題となっていました。会社としてもAIそのものの活用を様々な形で試みているような状態で、最新テクノロジーであるAIエージェントに興味を持ちました。その中でも「Nomatica」は、自社が持つマーケティングの独自ノウハウやコーヒーの調査データ等を入れて専用AIエージェントを作れる点が一番魅力的でしたね。
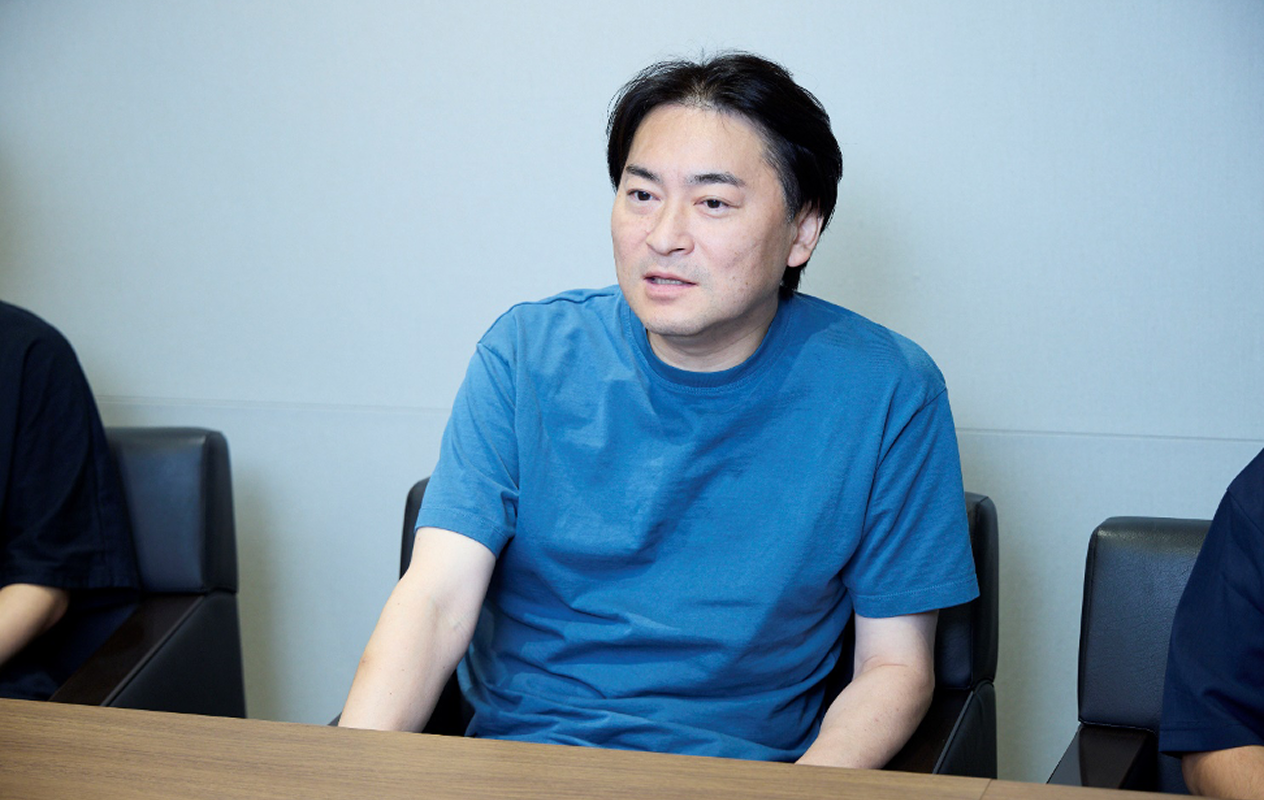
どのように導入を進めたのでしょうか。
平さん:最初トライアル※1という形で1ヶ月くらい導入した際に社内でヒアリングを行い、非常に有用ということだったので、まずは希望者から導入して活用を広げていく、という方向でやっていこうと決めました。
岡原さん:その後、説明会や勉強会を通じて活用が広がりました。特にDeep Researchや資料作成モードなど、今までにない新しい機能が出たときは、実際にデモ画面を映しながら説明したりしています。
斎藤さん:私はトライアルの終盤に触って、すぐに使いたいと思いました。それまで使っていた生成AIは一般論に寄りがちだったのですが、「Nomatica」は具体的で実務に直結する提案をしてくれる。そこが大きな違いでした。
導入当時の背景を教えてください。
斎藤さん:最初に驚いたのは各AIエージェントの専門性の高さです。他のAIと比べても、こちらの要求を深く理解してくれて、専門的かつ具体的な提案を返してくれるのは印象的でした。
あるとき、お茶の市場について50ページぐらいの資料を他のAIで読み込ませて提案させたんですが、一般論しか出てこなかったんです。そこで、「Nomatica」にも同様の資料から提案させたところ、専門性の高い回答が出てきて驚きました。やはり博報堂DYグループの生活者に関する独自データが効いていると感じました。
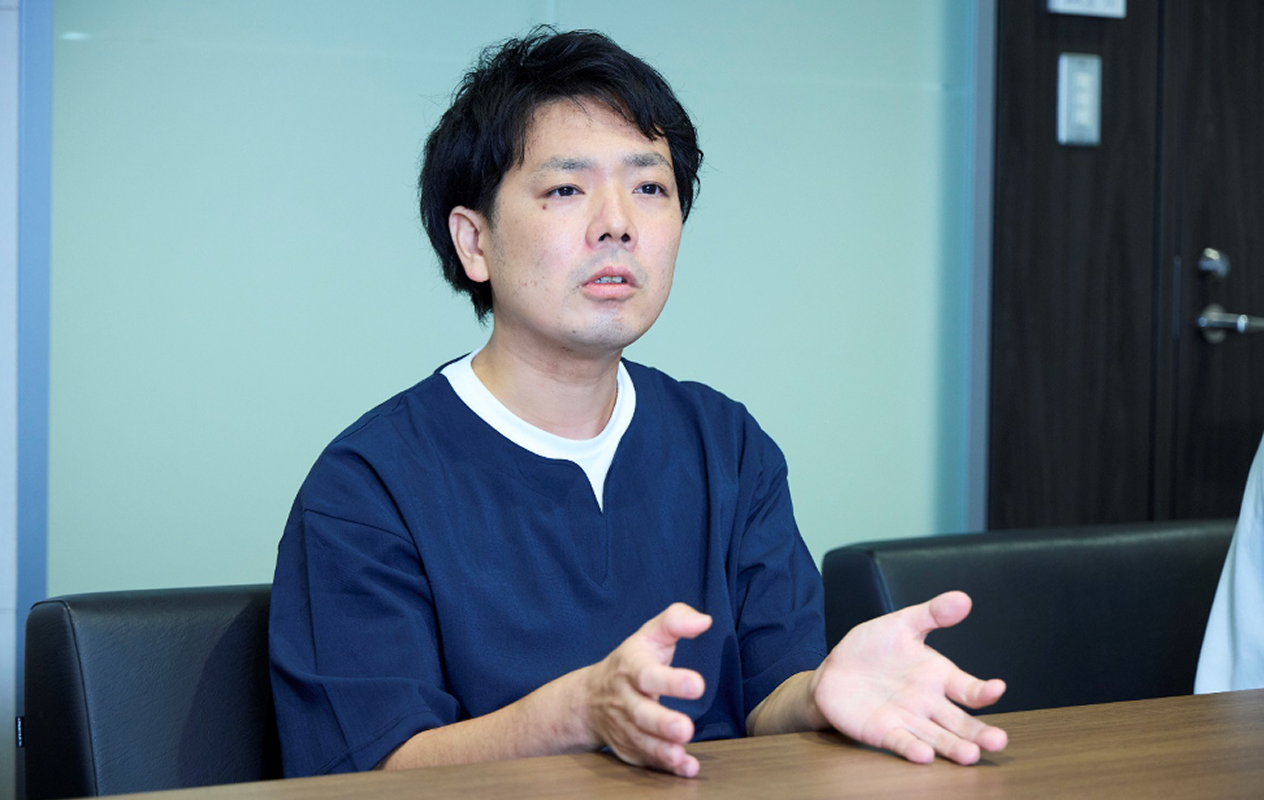
ほかによく活用している機能はありますか。
斎藤さん:実は業務用コーヒー以外の分野は自社データが少なく、Deep Researchを多用しています。ゼロだった情報が1や2になるのは大きいです。コーヒーにはない成分や他業界との関わりなども調べられて助かります。
AIに向き合うコツなどありますか。
斎藤さん:「Nomatica」に限らずAIに対する接し方全般に通じることだと思うのですが、100%の答えを求めるとやはり私が求めているものとは違うなということは正直あるんですね。
つまり、AIに対して結果だけを求めているとうまくいかないなと思っています。そうではなく、最終的なアウトプットを出すための自分のインプットとして活用するとか、こうやりたいなというアウトプットの補助として活用するという心構えであればうまく行くと思います。
社内での活用事例も教えてください。
斎藤さん:私の部署では競合調査をよく行うのですが、大手ではない競合の中には、メディアに記事が出ていなかったり、企業㏋もほとんど情報が載っていなかったりして、世の中に情報が出ていない企業も多いわけです。それが「Nomatica」で調べてもらうと、自分で検索するだけでは見つけられない情報を拾ってきたり、少ないデータからもしっかり分析し、深いレポートを出してくれます。そしてワードで出てきたレポートをそのまま「Nomatica」で資料形式にまとめ直してもらうことで業務効率化にもつながっています。上司やチームでのMTGにもそのまま使えるリサーチの精度とクオリティの高さで資料が完成するのが助かります。
岡原さん:例えば外部パートナーに依頼する時に、そもそも与件が整理できていないとか、課題がどこにあるか分からないとか、何を相談したらよいのか分からない状態ってよくあると思うんですよね。「Nomatica」であれば専門家に相談を持ち掛けるのと同じレベルの壁打ちが可能になったため、外部パートナーに相談する前の社内すり合わせなどが減りました。
山本さん:コーヒー市場調査員エージェント※2を作成し、過去の調査データをもとに方向性を提示してもらえたのは価値が大きいです。会社の事業戦略の方向性に関わるような、重要な資料の作成を依頼されていたことがあり、自分だけでは非常に悩ましい課題だったのですが、このコーヒー市場調査員エージェントに相談したところ、自分の気づかなかった視点やフレームワーク、見落としていたデータを提供してくれて何とか資料を仕上げることができました。まさにAIエージェントが事業の判断を左右したと言えると思います。
我々の部署は次から次へと調査を行うので、過去のデータを忘れてしまうこともあるわけです。今回のような掘り起しと提案がAIから出てくると、我々が持っている調査データの再活用につながりますし、そこはすごい価値を感じています。

今後の展望を聞かせてください。
山本さん:コーヒー市場調査員エージェントにもっとデータを追加して、私に聞かなくても「Nomatica」が答えられるようになると理想ですね。最終的には「自社のブランドマネージャー」のようなAIエージェントに育てることが理想です。
たとえば、いろんなメンバー、他部署の方から私宛に毎日質問が飛んでくるのですが、「Nomatica」のAIエージェントが育てば、少なくとも一次回答ができるようになる。そこでまずラリーをしてもらい、それでもっと聞きたいなっていう人だけが問い合わせに来るようになれば、メンバーもスムーズに回答をもらえるし、私の業務も楽になるしというところが、今後期待しているところですね。
岡原さん:毎月の定例報告なども自動化したいです。マーケターって定期的にデータをまとめて報告資料を作って…というような業務に時間を取られることが多い。そういった雑務をAIに任せることによって減らして、マーケター自身はよりクリエイティブな発想に時間を使えるようになればいいと思います。

まとめ
「Nomatica」は、調査から資料作成、戦略立案の壁打ちまで幅広く支援し、業務効率化だけでなく発想の幅を広げる存在として活用されています。導入初期の課題を乗り越え、今では「専属コンサルタントのようなAI」として定着。今後も機能拡張とともに、さらなる進化が期待されています。
- ※1 サービスローンチ以前の限定トライアル。2025年9月現在は受付終了。
- ※2 味の素AGF様が保持しているデータを用いて作成した専用AIエージェント